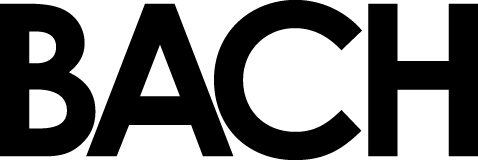自分たちで選ぶライブラリー
あなたの欲しい本は、既に目の前にあるのかもしれない。先日、あるワークショップをしたのだが、その現場で実感したことをちょっと書き留めておきたい。
本屋や図書館を訪れたときに、あなたはいつもこう思っているに違いない。「こんなにもたくさんの、多種多様の、似たような本の山の中から、いったい全体どの本を手に取れというのだ」。たしかに、わかる。本に関わる仕事をしているような僕であっても、近所の大型書店を訪れたときは「こんな本が出ていたのか!」と驚くこともあれば、お気に入りの1冊が絶版になってしまっており、ショックを受けることもしばしば。例えば先日、リチャード・バックの『イリュージョン』がもう出版されていないという事実を店員さんに教えてもらったときは、わが家の柱が人知れずシロアリに喰われていたような気持ちになってしまいガックリしてしまった。
膨大な中から抜き出し
一昨年、日本で出版された書籍の数は7万8349タイトルもあった。一日にならすと、約215冊もの本が生み出され、僕らの前を通り過ぎてゆく。あるものは、その存在に気付かれもせずに...。その原因を探っていくと、流通において書籍が貨幣化している問題や、ベストセラーのみへ偏重したアイデアに乏しい広告展開、人が本に求めるものの変化(考え続ける動機さがし→答えさがし)などなど、さまざまな要因が絡み合っている。それを深くえぐるとなると、もう少し紙面が必要になってしまうし、なんだかどんよりと暗澹(あんたん)たる気持ちになってくるので、今日はもう少し明るくて楽しい話をしよう。
僕は、愛知県立芸術大学という学校で非常勤講師をしている。毎週通うのは本業があり難しいのだが、毎年数度学校を訪れ、学生たちに自分の仕事について話す機会をもらっているのだ。愛知出身の僕にとっては故郷との関わりが増えるのはうれしいかぎり。中部地方の芸術大学の雄に通う学生たちは、首都圏の芸大生と比べておっとりしているように見えるが、芯はしっかりしているから僕も刺激をたくさんもらう。
そんな愛知県立芸術大学の芸術情報センター図書館で、年明けにワークショップを開催した。名付けて、「ライブラリー in ライブラリーをつくる会」。通常の十進分類法によって整然と並べられた図書館の本から学生たちが恣意(しい)的に何冊か本を抜き出して、図書館の中に小さな手づくり図書館をつくろうとする試みだ。
自ら訴えかける場に
50年近く前に吉村順三が設計した建築物でも知られる歴史あるこの大学。10万冊以上の蔵書を誇る図書館はじっくり眺めると、じつはお宝の山である。フランスはパリにあるポンピドゥーセンターが最もセンセーショナルだった1970年代のカタログがずらりときれいにそろっているし、1930年代にテリアード社から出版され、ピカソやマティスなどが描きおろしを寄稿したことで知られる大判のアート雑誌『VERVE』などもあった。初めてそこを訪れたときの僕は、興奮してばかりだった。しかも、博物館のガラスショーケース越しではなく、それらの本のページを自ら開けるなんて。
少し知っている人がふらりと時間を過ごせば、それらの本の面白さや価値に気付くはず。ところが、毎日その本棚の風景を眺めている学生たちは、既視感からか図書館の奥まで踏みいっていく必然もモチベーションも抱きにくいようだ。
そもそも図書館という場所は、これまでアーカイブという機能を一番のプライオリティーにしているところが多かった。目の前を通り過ぎる人に「この本、面白いですよ」と投げかけるより、何年かのちに検索してやってくるかもしれない誰かに「ちゃんと保存しておきましたよ」と、滞りなく手渡せるように。けれど、検索型の世の中に移行して以来、本との身体的接触が持てるこのような場所では、知らない本に興味を持ち、出くわしてもらうことが重要になっている。だからこそ、学生たち自らが「この本、面白いですよ」と訴えかける場づくりをする、こんなワークショップに至ったわけだ。
丁寧に本を差し出す
図書館のエントランス階段を上ったところに、学生たちがつくった段ボール製の小さな本棚が建ちあがる。紙とはいえ、案外しっかりした造りだ。集まった学生たちは25人ほどで、デザイン科の者もいれば、油絵科の者もいる。彼らを3つの班に分け、自分たちの本棚のテーマを決めるところからスタートだ。
まずは班の中で自分が人に薦めたい1冊をプレゼンテーションする。人が誰かに物を薦める動機の源泉は、自身の内から探すべきだからだ。ある学生は小説を、ある学生は自然科学の本を皆に紹介している。ここから共通項を見いだし、班としての1つのテーマに到達できるのだろうか? 不安もよぎりながら議論は続く。だが、みな自身の好きな本だから、その本のどの側面を推したいのか? どういう風に捉えているのか?というレベルの対話ができている。なんとか、それぞれの班は、ライブラリー in ライブラリーにおける本棚のテーマづくりに成功したようだ。
第1班は「かたち」をテーマにした本棚。第2班は「記憶」をテーマにした本棚。第3班は「新世界」をテーマにした本棚。従来ある分類法にはないけれど、さまざまなジャンルの本が交錯しうる楽しげなテーマだ。あとは、図書館の中を探検し、そのテーマに似つかわしい本を探すだけだ。普段は見向きもしない本、開いたことのない本、さまざまな未知がそこにはある。その中から何冊かを読んでみて、思い切って選び取り、自分たちのつくった本棚にならべる。本棚を再編集する作業だ。
いちどスイッチを入れてしまったら、学生たちはすごい集中力で本の狩りを遂行した。「うちの図書館にこんな本があったんですね」なんて言いながら、テーマに沿った本を探し出し、どの本の隣に並べればその本が映えるのかを真剣に悩む。本棚の雄弁性を考えながら、どの本のカバーをフェースアウトするのか議論し、必要を感じたら、本のレコメンド文も書く。本棚のテーマを知らせるサイン計画も重要だ。人が歩く導線を考慮しながら、どの場所にどんなサイズのサインを掲出するのかも重要だ。最後まで脇を締めて、丁寧に本を差し出すように。
必ずどこかに響く
最後にできあがったのは、見たことのないそれぞれ個性的な3つの本棚だった。図書館のどこかで眠っていた本たちが、学生たちから伝搬した熱を帯びて、いつもより得意げな顔をしながら小さなライブラリー in ライブラリーに並んでいる。
世の多くの図書館を眺めてみると、新刊予算が少ないとか、ベストセラーばかりに貸し出しが偏重しているという話題をよく聞く。けれど、リチャード・バックが『イリュージョン』のなかでこう書いていたことを思い出すべきだ。「ただ本をひらけばいい。そこが、きみにとっていちばん必要な箇所なんだよ」という言葉。読み手がオープンな気持ちになって本に向かいさえすれば、その本は必ず読者のどこかの部分に響く。そう、つまらない本なんていうのは、元来世界には存在しないのである。
幅 允孝
『SANKEI EXPRESS』2014.2.12 に寄稿
http://www.sankeibiz.jp/express/news/140212/exg1402121955004-n1.htm