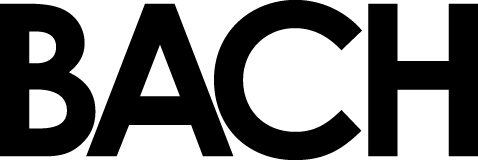知ることを止めない
ベージュ色で、ぶかぶかのスーツに身を包んだデヴィッド・バーンが、リズムボックス代わりのラジカセを持ってステージの中央に現れる。足元は白いキャンバス地のデッキシューズだ。彼はおもむろにプレイボタンを押す。シンプルできしんだ16ビートが聴こえてくる。名曲『サイコキラー』のはじまりである。
腰と内臓に直接響く
これはトーキング・ヘッズが1983~84年に行ったライブツアーの様子を、のちに『羊たちの沈黙』で知られることになるジョナサン・デミ監督が撮ったドキュメンタリー映画『STOP MAKING SENSE』(※1)の冒頭だ。日本語でいうと「意味を求めることなんて、やめてしまえ」というところだろうか。
10代の後半、トーキング・ヘッズのやることなすこと全てが格好よく見えていた僕は、花屋のアルバイト(かわいらしい花でなく、葬儀の供花の方が多かった)で稼いだお金を握りしめ、大きな肩パットの入ったぶかぶかシルエットのコム・デ・ギャルソンのジャケットを買いに出掛けた。バーンが着ていたのはもちろん特注だったと思うけれど。
ともあれ、この映画ではデヴィッド・バーンのセンスが際立っていたと僕は断言しよう。たった一人で演奏する1曲目のステージに続き、2曲目で一人、3曲目でもう一人と舞台上の演者がどんどん増えてゆき、最後の楽曲が終わったときにはサポートメンバーや観客をも巻き込んだ大団円で幕をとじる演出にしびれまくった。また、1979年に発表したアルバム『Fear of music』に収録されている『I Zimbra』以降、バーンが傾倒したアフリカン・リズムも、このライブツアーで最高潮を迎えていた。Pファンクの屋台骨をつくったバーニー・ウォーレルが準メンバーとして加わっていた当時のトーキング・ヘッズは、なんというか、腰と内臓に直接響いてくるバンドだった。
しかも、トーキング・ヘッズは音楽性だけでなく、無意味そうな意味性を持ったメッセージやら、PVや舞台の演出法、ファッション、アルバムのジャケットデザインなど、あらゆる角度から「みられる」ことを意識していた点も新鮮だった。実際のところ、日本に輸入された当時は、トーキング・ヘッズ=「おしゃれ」野郎の代名詞として扱われていたらしい。かくいう僕だって、女の子になんとかモテたくて聴き始めたようなものだったし(実際、肩パットの大きすぎるジャケットでは、モテるはずもないのだが...)。でも、そんなよこしまな目的だって、いいじゃないか!と声を荒らげるまでには、もう600ワード程待っていただきます。
大好きな曲の本当の意味
さて、彼らのライブ映画におけるハイライトを1曲挙げろといわれたら、『Once in a life time』になるだろうか。ブライアン・イーノとつくった最後のアルバムとしても知られる『Remain in Light』(※2)。トーキング・ヘッズを代表するアルバムの4曲目。サビの抜け感が珍しく爽やかで、歌詞もよく分からないまま車の中で熱唱したりしたものだ。
だが先日、町山智浩の『本当はこんな歌』(※3)を読んで、この曲の意味を知り驚いた。この本は、僕らが普段、音としてしかとらえておらず「ふふふーん」と適当に口ずさんでしまう名曲たちの歌詞が訴える「本当のところ」を教えてくれる、ありがたくも少しがっくりくる1冊なのだが、まさか『Once in a life time』が「中年の危機」を迎えたおじさんのノスタルジーソングだったとは...。サビの部分でバーンが歌っていたのは、ふと立ちどまって人生を見返したときの違和感。もっとしゃれた曲だとばかり思っていたのに。
ちなみに町山のこの本は、フットボールスタジアムで僕が意気揚々と唄っているホワイト・ストライプスの『Seven Nation Army(七国軍)』は、メンバーの片割れであるジャック・ホワイトが子供の頃「救世軍(サルベーション・アーミー)」を聞き間違えて出てきた言葉だなんてことも伝えてくれる。レディオヘッドの出世曲『クリープ』に関しては、ライブ会場で何万人もが「僕はキモい、僕はイケてない」と合唱していることなんだとも教えてくれる。「知る」って恐ろしいことですね。
でも、僕はやはり知ることを止めたいと思わない。知らないことが幸せだとも思わない。不思議なことかもしれないが、ものを1つ知るたびに、疑問は2つ以上湧いてくるものだ。だけど、疑問と向き合い続ける毎日が、僕はたのしい。すぐに答えを求められがちな世の中だけど、考え続けること自体が面白いから僕は本を読んでいる。多分。
体が反応したものを追い続ける
今回の原稿はあえて固有名詞をたくさん入れたから、読み難くて仕方がないかもしれない。けれど、モテたくてデヴィッド・バーンに心酔した20年以上も前の僕は、そのバーンの糸をたどりながら、たくさんの彼らの仕事を知り、多くの映画や本や人物に出くわした。最近は外部記憶が発達し過ぎているから、困ったらグーグルに尋ね、分かったら忘れてしまうよう脳みそが習慣づけられている。
けれど、インターネットがなかった当時は、必死で雑誌の細かなキャプションまで読み、間違えたり、肩すかしをくらったりして、何とか自分の好きな世界を形づくっていた気がする。もちろん、ネットの世界は便利なのだけど、自分の芯をつくるには、よこしまでも何でも、自分の体が反応したものを素直に、愚直に追い続けるしかないと思うのだ。
幅 允孝
(※1)ジョナサン・デミが監督を務める本作だが、実は撮影も『ブレードランナー』のジョーダン・クローネンウェスが担当。アスリートのように体を駆使して唄い、踊るバーンのパワーを感じられる映像はさすがの一言。
(※2)軽快なアフリカン・ビートで始まるこのアルバムはトーキング・ヘッズを世に知らしめる契機となった名盤。サポートメンバーで、後にキングクリムゾンのメンバーになるエイドリアン・ブリューの変態的なギターも必聴。
(※3)当時の社会背景なども考慮することでその歌の本来の姿を浮かび上がらせる。「ラブソングだと思っていた曲が実はストーカーの心理を歌ったものだった」なんて悲しい事実も。アスキー・メディアワークス、1080円。
『SANKEI EXPRESS』2014.9.2 に寄稿
http://www.sankeibiz.jp/express/news/140902/exg1409021605004-n1.htm