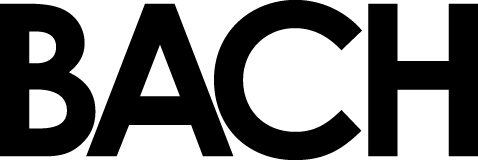認知症患者に本は必要か?
認知症患者のための本棚。果たしてそんなものが必要なのだろうか?とあなたは考えるに違いない。
11月の初旬に新しくできる佐賀市内の病院に本棚をつくる仕事をした。「さやのもとクリニック」という名のその医院は心療内科、なかでも認知症のケアを中心にした病院だ。そこの院長である亀谷さんと1年以上も前から何度も意見を戦わせながらできあがったライブラリーだが、果たして患者さんにはどういうふうに届くのだろうか? 今は期待と不安が入り交じったような気持ちだ。
僕たちの好きな本を持っていっても、おせっかいにしかならない。そんなことはよく分かっているつもりだ。だから、ここの本棚をつくるときも、他の本棚と同じよう、どんな本棚にすべきなのか?のインタビューを重ねた。中でも、実際の認知症介護を経験された方々に本をお見せしながら率直な感想を聞いたインタビューでは、こちらの想像を超えるリアリティーを突きつけられる。スーツケースにいっぱいの本を詰め込み、佐賀まで出向いたのだが、まず重い本はNG。せっかく運んできたのに...。僕らの体は簡単だと思っているが、大きくて重たい本を手に持ってめくることは、相当な筋力が必要とされる。
しかも、ほとんどの患者さんはテキストを読める状態でもない。小さな文字を続けて読む持久力は著しく損なわれており、どこからでも読み始め、どこでも終わることができる本や、ぱらぱらとページをめくるだけで楽しめるような本にしか興味を持ってもらえない。つまり、写真や絵、イラストなど視覚的に楽しめる本を中心に選書をするしかなかったのだ。
写真集やアートブックというと、随分と高い敷居をイメージする方も多い。けれど、これらの本が本来あった文脈から離れると、急に認知症病院でも面白がってもらえる本に変貌するのには驚いた。例えば、『カタログで知る国産三輪自動車の記録。1930~1974』という三樹書房の一冊。この出版社はかなり古い時代のものを含めた車関連の書籍がとても強い、カーマニアにはよく知られる版元だ。けれど、農業従事者の多かったこの佐賀の土地では、車好きという視点ではなく、かつての自分の仕事道具という目線で当時のオート三輪の写真や広告を見てくれる
「記憶の断片」掘り起こす
認知症患者の方は、短期記憶が苦手である。「ついさっき」のことが最も損なわれてしまう可能性が高いから、今朝のご飯の話などはうまく進まないことも多い。けれど、長期的な記憶はしっかりと彼らの中に埋まっている。それをどう掘り起こし、触れることのできた地中の蔓(つる)を、どう引き上げるのか?が本棚づくりの肝となった。
地域のわらべ歌や懐かしい遊びがつまった『日本伝承のあそび読本』、口頭伝承で伝わる佐賀の郷土料理を県内の地域別、季節別にまとめた『日本の食生活全集41 聞き書 佐賀の食事』、大きな図版でかつての農工具を図鑑形式で紹介する『シリーズ昔の農具1 くわ・すき・田打車』など、佐賀という地場に依拠した懐かしい記憶の断片が棚には並ぶことになった。
もちろん、『吉永小百合ブロマイド写真集』や『日本映画ポスター集 東映活劇任侠篇』『昭和レトロ家電』『60年代 街角で見たクルマたち【日本車・珍車編】』『懐かしのホーロー看板 広告から見える明治・大正・昭和』のように、一時代を風靡(ふうび)した国民的記憶も患者さんたちの地中を掘り起こすヒントにはなる。だが、まずは彼らが暮らしてきた日々に関する卑近なところから探り始め、やがて大きな記憶に対する本を差し出した方が思い出す流れがよさそうだった。身近な最小単位から記憶もかたちづくられているのだろうか?
思い出さないのもまたいい
認知症の予防や進行抑制の方法として回想法というものは確かにある。僕も素人ながら何冊かそれに関する書物も読んだし、それをやっている現場も見せていただいた。だが、僕が気になったのが、懐かしの写真を教科書的に配置した回想法のテキストブックを患者さんに見せ、何も思い出せなかったときに漂う落胆感がどうしても腑(ふ)に落ちなかったのだ。何かを思い出すことを目的化した時点で、それは愉しい読書ではなくなる。僕は、それとはまったく逆のアプローチ、つまり「何かを思い出すのもいい」けれど、「思い出さないのもまたいい」というスタンスで本を手に取ってほしかった。思い出や記憶は強要されてコントロールできるたぐいのものではない。そして、本はあくまでも、読み手の気侭(きまま)さにぴたりと寄り添っているくらいがちょうど似合うと僕は考えるからだ。なぜなら本は、待ってくれるものだから。
今回の本棚では、もうひとつ本だからこそできることに僕は気づいた。それは、本をめくる手は止めることができるという点だ。当たり前と思われるかもしれないが、これが映像では難しいのだ。
映像は視覚に強く訴え、そこに集中させるゆえ、特別養護老人ホームなどではテレビでの映像を流しっぱなしにすることがあると聞いた。もちろん夢中になるということは徘徊(はいかい)などのリスクを軽減することにつながる。
だが一方で、映像を見続けることはかなり受動的な視覚情報の受け取り方になってしまう。トラクターの写真を眺めていた誰かが急に放つ、「お、このクボタT15、月賦で買ったんだよ!」なんていう言葉。本ならそのページで立ち止まることができるが、リモコンではそんなにうまく「一時停止」ボタンは押せない。その視覚情報と触れ合う時間を自分で牛耳れるところに、本の魅力はあったのだ。
患者家族のストレスアウトも
実はこの「さやのもとクリニック」の本棚は、これで機能の半分だ。もう半分は、介護で本当に大変な思いをしている家族のためのストレスアウト用の本をそろえることになった。正直にいって、認知症患者を支える家族に本を読もうなどという精神的余裕はまったくない。けれど、通院型のこの病院では、先生が診察をしているわずか20分だけ許される安息の時間になんとか彼らの心と体をもみほぐしたいと考えた。毎日の介護に集中し、気を配り続ける彼らに少しでも視点を変換できるヒントを差し出すための本。20分だけでも、未来を向いてもらうための本。ちょっと遠い先のことかもしれないけれど、次の旅先を考えたり、ふと空を見上げたり、そんなことの背中押しぐらいだったら本だってできるかもしれない。そんな気持ちが詰まっている。
この病院の本棚は、これで完成なのではなく、やっとスタート地点に立ったところだと思っている。これからも現場の生の声と向き合いながら、本だからこそできることを少しずつ確認していくしかない。そんなふうにして認知症患者のための本棚をつくっていくしかないのだ。
幅 允孝
『SANKEI EXPRESS』2015.11.4 に寄稿
http://www.sankeibiz.jp/express/news/141104/exg1411041620005-n1.htm