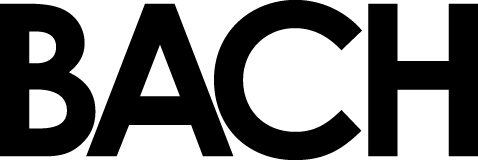幅允孝は『土俵の周辺』を読んで、あの時の相撲を思い出す
白鵬は確かにすごい。だけれども、僕にとってのヒーローはいつまでたっても千代の富士なのだ。北の湖を破って大関昇進を決めた優勝決定戦は、僕の最も古い相撲の記憶。暑い夏、婆ちゃんの部屋でカルピスを飲みながらみていた。筋肉質の小さな体で速攻と上手投げを得意とするスタイルは、素人の子供でも虜にする鋭さがあった。まわしが黒色に変わってからの最盛期は、彼の「凄み」に見とれていたと思う。
1989年の3月場所では、14日目に大乃国を破って優勝を決めるものの肩を脱臼。表彰式では片手で賜杯を手にしたのだが、その背中の凛々しさに、少年幅は惚れぼれした。
と、懐かしい相撲の記憶が呼び覚まされたのは全部『土俵の周辺』を読んだせいだ。著者の岩崎友太郎は1946年生まれの「相撲狂」。僕の調べた限りでは、他の著書はない。大の相撲ファンが、好きで好きで書いてしまった「相撲を支える人たちの群像劇」というとわかりやすいだろう。短編のような形でまとめられた「土俵周り」の人々を、岩崎は全ページから溢れる相撲愛で優しく包みながら綴っている。
両国国技館近くにあるキングサイズの衣類専門店「ライオン堂」の秘話。なんでもかんでも巨大サイズの衣類を扱う名物店は、編機を横に使うことによってできた。関取用パンツの異様に巨大なさまは、店主の寛容さと比例する。
幕下力士 盛風力と九州女の大恋愛も面白いエピソードだ。のらりくらりと力士をしていた男が引退後に一念発起。当時はどこにもなかった「塩ちゃんこ」を発案するまでの道のりは愛ゆえに辿り着いた味か。
廃業した元力士が相撲甚句の唄い手として、もういちど土俵に立った日の話も隠れた人の歴史だ。今では伝説の唄い手といわれる大納川憲治は30年もの間、古くから伝わる相撲甚句を一人で唄い続けたという。流行りの相撲甚句ではなく、昔ながらの唄を彼が貫いた理由は一読の価値があるはず。
27代立行司木村庄之助の話も忘れがたい。盛岡の旅館の息子だった彼は9歳の時に行司になることを決意し、角界入り。小さな子供を手放した両親の辛苦も想像できるが、父が息子に送った短い手紙がじつにいいのだ。親が子に託すべき思いが結晶した短くも強い言葉。しかも、今年90歳を迎える名行司は、まだ父からもらった手紙を大事に持ち続けているというではないか。
と一気に書いてきたが、果たしてこういった新刊がなぜいま出版されるのか?僕にはわからないが、そこがいい気がする。というのは、相撲という国技は結局いつもすぐそばに在り、僕らの記憶を巻き込みながらこれからもずっと続いてゆくものだからだ。あの裸の男たちのぶつかり合いはスポーツではなく儀式であり、礼節や人情を思い出すきっかけなのだと本書を読んで確信する。ふいに思い出す自分にとっての相撲の思い出。そのトリガーをひくために、温かい人間模様に耳を傾けてみるのも悪くない。
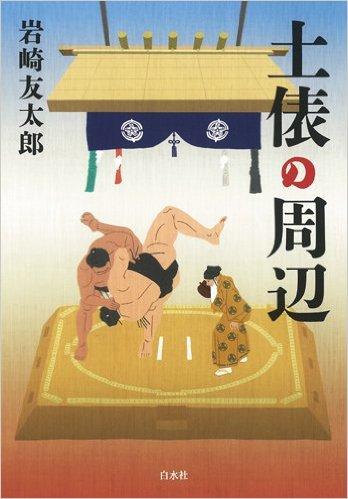
『土俵の周辺』(岩崎友太郎著/白水社、2,400円+税)
ケトル vol.23 June 2015に寄稿