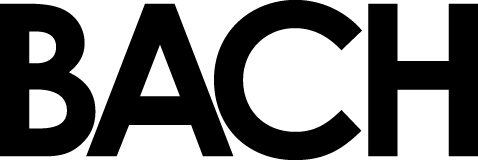「すこし・ふしぎ」な九井諒子
先日、「このマンガがすごい!2016」が発表され、オトコ編の1位に『ダンジョン飯』(ビームコミックス、670円)が選ばれた。それだけではない、「コミックナタリー大賞」や「THE BEST MANGA 2016 このマンガを読め!」でもこの作品は1位に選ばれ、にわかに話題沸騰という作品である。
九井諒子が描くこの物語は、地下ダンジョンに棲む魔物たちを主人公の戦士らが調理して喰らうという一見不可思議な食マンガ。ところが、魔物たちの生態と、その料理法を限りなく厳密に描くことで、読者の共感を得ることに成功している。ファンタジーとしての食マンガは、『トリコ』や『ミスター味っ子』(あえてファンタジー枠でくくっておきましょう)など先駆者がいなかったわけではない。けれど、ちゃんとおいしそうな匂いが漂ってくる幻想食マンガは、初めて読んだ気がする。
本気度伝わる幻想食
『魔女の宅急便』などで知られる児童文学作家の角野栄子は、絵本「おばけのアッチ」シリーズで「いもむしグラタン」や「おばけカレー」を生み出しているが、「ファンタジーの中でも必ず食べたくなるものを」と語っている。『ダンジョン飯』に登場する「人喰い植物のタルト」も、ありえないと知りつつ胃袋に訴えかけてくるのは、レシピの細やかさが秀逸だからだろう。タルト台をどんな素材でつくるのか? 生地のつなぎをどんな種類にするか? 作中では、スライムかバラセリアという食人植物のゼラチンしかつなぎの選択肢はないのだが、誰もが想像できる調理方法に魔物的素材を組み合わせることによって、奇妙なリアリティを獲得している。だから、「動く鎧のフルコース」や「茹でミミック」が出てこようとも、作者の食に対する本気度を読者が感じ続けることができるのだ。
そんな様に2015年大ブレークした九井諒子であるが、じつは僕が推したいのは短編だったりする。初めて手に取ったのは『ひきだしにテラリウム』(イースト・プレス、821円)という33の短編マンガが収録された1冊。2013年に発売したものだ。もともと星新一やリン・ディンのような短さゆえに増幅する物語が僕は好きなのだが、九井のマンガにも凝縮した世界観を一気にかたちづくる物語構成力と、それをいとも簡単にほっぽり出してしまう、気持ちのよい余韻がある。
多視点でつづられる構成力
たとえば、「春陽」という6ページの作品は、冒頭の1コマ目でこんな会話が交わされる。「知り合いの飼ってる人間が子供生んでさ 里親をさがしてるんだ お前どうだ?」。初めて読んだ方は首をかしげるに違いない。要は、僕らが猫の里親を探すようなお話。ペットとしての小人が世の中に普通に存在する世界で、その飼い主と飼われている小人の日々をつづったマンガだ。もらってきた4カ月の女の子は、最初こそ慣れぬ環境で泣いてばかりいるものの、少しずつ飼い主と関係を結んでいく。散歩中に野良人間と出くわし喧嘩をしたり、一緒にお風呂にはいったり、日々は続く。だが、5ページ目に差し掛るあたりであんなに小さくて可憐だった小人も歳をとり、おばあちゃんになってしまう。まるで飼い猫が少しずつ命を小さくしていくように。時間の流れが異なる2つの生き物が、一緒に暮らすことについて見事に描かれた不思議な6ページに脱帽してしまうが、九井が見事なのは、それに続く「秋月」という6ページの作品では、飼われている側の視点から、また別の物語を綴るところだ。
彼女の作品の魅力のひとつに、多視点のユニークさがある。同じ本に収録されている「えぐちみ代このスットコ訪問記 トーワ国編」では、貧しくも美しいトーワ国を訪れた観光客の視点と、そのツーリストを「こんな汚い国の写真なんか撮って何が楽しいのか」と軽蔑する地元のホテルで働くイケメンの視点が交錯する。ひとつの事実を別の方向から照らすことによって、まったく別の物語が浮かびあがる。しかも九井はあえてその両者の視点を別の画風にすることによって際立たせた。エッセイ・マンガ風の旅行記とシリアスなタッチの絵を8ページ作品の中でうまく同居させているから驚くのだ。
読み手が納得いくSF
別の短編「恋人カタログ」は、社長令嬢だが地味で面白みのない女と付き合う主人公が、タイムマシンの助けを得て未来のガールフレンド候補のデータを送ってもらうというストーリー。ドラえもん18巻にある「ガールフレンドカタログ」へのオマージュである。驚きのオチはドラえもんと異なるのだが、共通するのは、2作品のSF感。サイエンス・フィクションのSFではなく、藤子・F・不二雄が提唱した、「すこし・ふしぎ」という意味でのSFである。
思えば、ケンタウロスの嫁さんと普通の類人猿である夫の生活様式の違いをベースに、「馬人」と「猿人」の社会的軋轢(あつれき)を描いた「現代神話」(『竜の学校は山の上』に収録)も「すこし・ふしぎ」なお話。『ダンジョン飯』の萌芽(ほうが)ともいえる、村の儀式としてジビエ料理を楽しむように龍を食べる「龍の逆鱗」も、「すこし・ふしぎ」なお話。
1点だけ明らかに突拍子がないのに、それ以外の世界の描き方があまりに普通ゆえ、「確かにあるかもしれない」と読み手の納得を誘うのが、九井SFの源泉だ。これからも、彼女の生み出す「すこし・ふしぎ」に注目していきたい。

「すこし・ふしぎ」な九井諒子の作品たち(右端『ダンジョン飯』、中央『ひきだしにテラリウム』=2015年12月24日(提供写真)
『SANKEI EXPRESS』2015.12.27 に寄稿