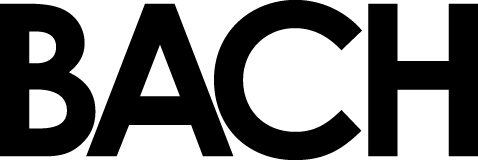幅允孝は『台湾生まれ 日本語育ち』を読んで個と国について考える
幅允孝は温又柔作品を読んで、個と国について考える
2016年の年明けは卒論だ、解散だと慌ただしいニュースが多かった。そんな中、台湾総統選のニュースも連日届く。民進党、圧勝。蔡英文、初の女性総統へ。そのようなタイミングで僕が日々読み進めていたのは小説家、温又柔の『台湾生まれ日本語育ち』という1冊だった。台北で生まれ、3歳から日本で暮らす彼女が自身のルーツと言葉を巡り、考え続けた日々をエッセイにしたものだ。白水社のHPで連載していた頃から(その時は『失われた"母国語"を求めて』というタイトルだった)楽しみに読んでいた作品だったから、やっとの書籍化は嬉しい限り。じつは彼女のデビュー作『来福の家』に出会って以来、僕は温作品の愛読者なのだ。
彼女の小説は、小さな頃の記憶を辿りながら、自身をアイデンティファイするものを丁寧に紐解く。日本語、台湾語、中国語という3つの母語の間で揺れながら、自分自身の場所を見定めようとする。拠りどころのなさを作品の推進力にする小説は多々あるが、それを朗らかな温かさに転化できる書き手はそんなに多くないように思う。
世界の境界が曖昧になってくれば、当然のことながらその狭間に生まれてくる者も多くなる。世界文学を見渡す趣味がない人だって、U23サッカー日本代表が立つフィールドや、近頃の小学校の教室を垣間見れば、幾つもの国にルーツを持った人が増えている状況を、自然な変化だと受け止めることができるだろう。だが、外側から見える景色と、内側から見えるものは明らかに違う。
このエッセイでも、彼女は運転免許の更新手続きで自身が外国人だということを再認識し愕然とする。日本で30年以上暮らし、この国の文化や習慣は体に染み付いている。もちろん、彼女が自身の考えを伝える武器とする言葉も日本語だ。けれど、彼女は外国人登録証明書を携帯しておらず、その場での交付が叶わなかった。彼女の心の内と、書類の上の事実とはまだまだ深い溝がある。
そんな中、本書のハイライトのひとつといえるのが2102年に行われた台湾総統選挙のエッセイである。日本で投票ができない彼女は、2年以上入国していなかったゆえ台湾でも投票できなかった。けれど、選挙当日に彼女は台湾へと向かい、家族と共に時間を過ごす。そこで感じた台湾という国への想いが、今年2016年の選挙へと彼女を駆り立てたのだろう。残念ながら本書には収録されていないが、先ごろ白水社のHPに書かれた「台湾総統選挙を終えて」とあわせて読めば、彼女の「ふしぎな疎外感」をより近くに感じることができるはずだ。
日本語を主旋律にしながら、通奏低音で台湾語と中国語を響かせる温又柔の作品は、個にとって国家とは何か?を僕に考えさせる。そして、彼女が描く静かで強い決意は、どんな国籍の人の背中だって押してくれると思うのだ。

「台湾生まれ 日本語育ち」(温又柔著/白水社、1,900円+税)
ケトル vol.29 February 2016 に寄稿