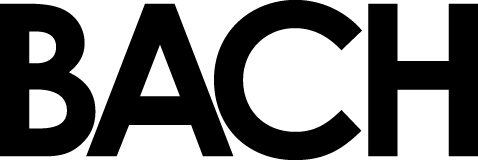後醍醐天皇がSNSをやっていなくてよかった
本が1000年後に残るのか?というお題をいただいたのだが、そもそも何をもって「本」というのだろうか? 書物の歴史を紐解けば、巻子本(いわゆる巻物ですね)から折本、和綴じ製本と「本」の形は時代と技術に応じて、どんどん変化している。最近はEペーパーや液晶で読むテキストが主流になっているが、インターフェイスの最終目的地がその「消失」だとしたら、SFで描かれるような中空に浮かぶテキストを皆が読むような時代がやってくるかもしれない。まあ、問題は、「何で」読むのか? ではなく、「何を」読むのか? という点に尽きるのだが。
ただ最近は、テキストが正確に残りすぎるのもどうかと思う。新年早々に話題を提供した某タレントのLINE流出ではないが、細やかなやりとりがいちいち「残りすぎる」ライフログ社会というのは考えものだ。例えば、後醍醐天皇や足利尊氏のSNSが明確に残っていたら、現代の天皇制の根幹が揺らいでしまうかもしれない。水戸光圀が編んだ『大日本史』や『太平記』など、幾つもの不完全な書物を読み解きながら、自分なりの考え方を形づくっていくのが書物を読む楽しさの一部なのだと思う。
アメリカの書店に行くと、バイオグラフィ・コーナーの広大さに驚くのだが、それは彼らの「歴史を作らねば!」という切迫観念の裏返しともいえる。ただ、自身が書いた自叙伝と、ほかの誰かが書いたものではまったく違う印象を受けるのが面白い。マイルス・デイヴィスの自叙伝を読み比べてみるといい。一方、ログ社会がこのまま続くと、正確すぎるバイオグラフィしか書かれなくなって、随分つまらなくなりそうだ。少しでもエピソードを盛ろうものなら、過去のログを突きつけられ集中砲火を浴びてしまう。明確すぎる断片が、歴史を別の意味で歪ませる可能性だってある。後世の人は、誰かが残した人生の隙間を想像する作業が楽しいはずだし、本来はそこに物語が生まれる。余白のない人生には、色気もないと個人的には思うのだけれど......。
結局、1000年後にどんな本が読まれているのかなど分からない。1895年に書かれた樋口一葉の『たけくらべ』が、2015年には川上未映子によって現代語訳されるのだ。日本語が、現在の文法やリズムとまったく違ったものになっている可能性は高い。ただ、ひとつ確かなのは、そこに誰かが生きている限り、人は人について書き続けるのだろう。なんといっても「書く」という行為は、最も簡単に始められ、お金のかからない痕跡残し。愛や幸福や安堵だけでなく、嫉妬や怒り、絶望など、清濁入り混じった人の感情が続く限り、なんらかの書き物(もはや「本」という名ではないかもしれないが)は、1000年後もそこにあると思う。まあ、あまり悲観的に考えず、レッツポジティブに推移を見守りましょう。
TRANSIT31号(2016年3月18日発売)に寄稿