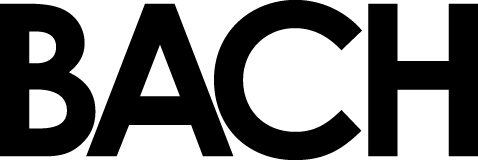幅允孝は小説版『あの花』がアニメの面白さを増幅させると思った。
日本のアニメ業界は大ヒット作に恵まれただけでなく、海外販売や配信、イベントや商品の売上増により業界全体で盛況。一方、僕が関わる本の世界は、よい調子と決して呼べない。けれど、物語を味わう根っこは相方変わらないはずだと最近考えているのでその話を。
2年程前、ある女子高の図書室企画をしたのだが、インタビューで彼女らが口にする読書体験はほとんどがアニメからの影響だった。折角だからと守備範囲を無理やり広げる気持ちで深夜のアニメ作品を幾つか視聴してみたのだが、これが意外なほど面白く、今では「1話チェック」をしっかりして1クールにつき数本のアニメを視ている。時間は足りないが、両者の結び目を考えることが本を伝達するヒントになるとも思っている。
映画と本の関係は昔から幾度も語られており、「原作を読んでから観る」派と「観てから原作」派の論争はずっと続いている。多くのアニメも原作を持つから「作品」と「原作」の対比はできるのだが、今回注目したいのは、アニメありきのノベライゼーションについてだ。アニメを入り口にしながら、どれだけ読書を習慣化してもらえるのか? 本の側に立つ僕は、ここがヒントになると思っている。
例えば、2011年に放送され大ヒットしたアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』(以下『あの花』)は、放送に先行して「ダ・ヴィンチ」誌で小説版の連載が始まり、翌年までそのノベライズは続いた。アニメの脚本を手がけた岡田麿里が記したその小説。単純にストーリーをテキスト化したのではなく、小説世界独特のアレンジや、シーンの追加と割愛、そして時系列の組み替えを行い、アニメ作品や登場人物の深部を捉えることに成功したノベライゼーションだったと僕は思う。
知ってる人は知っていると思うが、『あの花』は、水難事故で亡くなった少女めんまが5年後の夏、仲間たちの前に再び現れるという黄泉帰りの物語。高校生になっていた仲間たちは、事故当時とまったく異なる状況に身を置いていたが、それぞれが罪の意識やトラウマと向き合うことで少しずつ前向きに歩んでいく。偶然このアニメを視聴していた僕は、驚くほど号泣しながら「ノイタミナ」枠を毎週視ていたわけだが、この小説を読むことで「ぽっぽ」の強い贖罪意識や「つるこ」の歪んだ愛の形も知ることになる。
一話につき約22分のアニメでは拾いきれない心象も、岡田は小説世界で一人称と三人称を自在に使い分けることにより、細やかに描き切ることに成功した。しかも、面白いことに小説版を読んだ後にアニメを再度視聴すると、気づかなかった登場人物の表情やセリフの間合いなども妙に響いてくるから不思議なものだ。
かつては小説世界を隅々まで味わうために批評や書簡集などが機能していたが、いまはアニメを存分に味わうために小説が背中押しをするのかもしれない。そんな立ち位置でも受け入れて、テキストに没頭する愉しみを伝えていかないと、時間の奪い合いに本は敗北してしまう気がする。

ケトル vol.35 February 2017に寄稿