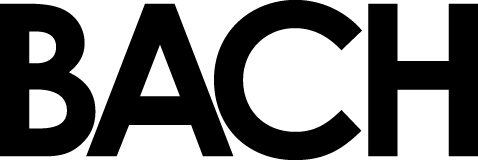幅允孝は新しい熊谷守一展をみて『蒼蝿』を読み直した。
幅允孝は新しい熊谷守一展をみて『蒼蝿』を読み直した。
竹橋の東京国立近代美術館で開催中の熊谷守一展をみにいった。
熊谷は東京美術学校(現・東京藝術大学)時代に同期の青木繁らをおさえて首席で卒業。
にもかかわらず、80歳を過ぎてやっと世の中に作品が知られるようになった洋画家である。僕は随分と「やる気まち」の長い爺様だと思っていた。
真っ白で伸びきったあご髭をたくわえ、言行録の『蒼蝿』では仙人然とした泰然自若の言葉ばかりを連ねているから、そんなイメージを抱いたのかもしれない。「絵を描くより、ほかのことをしているほうがたのしいのです。欲なし、計画なし、夢なし、退屈なし、それでいていつまでも生きていたいのです」などと正直に告白してしまう熊谷翁93歳。
ほかにも「子供が病気になって困ったときでも、そのために絵を描いて金にかえるということはできませんでした。やる気のあるときに描くだけです。気のないときに描いても何にもなりませんから、そういうときには描きません」とも仰っている。こんなアフォリズムや晩年に受勲を断った逸話などが先走りして、熊谷守一の浮世離れしたキャラクターができあがった。
実際、熊谷守一の作品というのはとてもシンプルでユーモラスな油絵が多い。猫や花、鳥、虫など身近なモチーフを凝視し、多様な色と潔い線を用いてそれらを表現する。それでいて、その線は導かれた必然をも感じるのだから絵には説得力もこもる。例えば、有名な「眠り猫」(1959年 油彩)という作品は、猫をずっと眺めた経験のある人の共感を強く誘う。猫の背の柔らかさや温かさが仙人=守一によって選び抜かれた一本の線によって命を吹き込まれたと思えるからだ。
ところが、今回の展覧会は違っていた。もちろん、会場では熊谷守一の優れた作品を鑑賞できるのだが、「守一スタイル」に到達する過程を丁寧に紐解くことに力点をおいていた。つまり、彼は決して仙人ではなかったと訴えかけてくるのだ。やがて、みなが愛する「守一スタイル」に到達することを知らずに試行錯誤を繰り返し、苦しむ人=熊谷守一にシンパシーを感じさせる展覧会だった。
「轢死」など光と闇を描くことに執心した初期作品の見方や、科学的なアプローチを用いて色彩について考えていた様子、そして海外作家からの影響などパブリックイメージを大きく覆す熊谷守一展に僕は勝手ながら大きな拍手を送りたい(今年度末まで開催中なので是非)。
と同時にここでいいたいのは、『蒼蝿』などに記されている彼の言葉の意味もこれまでとはまったく違って読めるということだ。彼のとぼけて飄然とした言葉の数々も、世界の成り立ちを緻密に考察した男が辿り着いた地平なのだろう。そう考えると、「やる気まち」の奥行きにまで、再度潜ってみたいと思うのだ。同じ本でも二度と同じようには読めないとは、まさにこのことですね。

ケトル vol.41 February 2018に寄稿