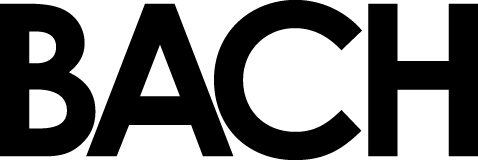幅允孝は『幸福書房の四十年』を読んで、ある誓いを胸にした。
幅允孝は『幸福書房の四十年』を読んで、ある誓いを胸にした。
代々木上原駅前にあった20坪の小さな書店「幸福書房」。惜しまれつつ今年2月20日に閉店してしまったのだが、その店を40年近く切り盛りした岩楯幸雄さんの本屋一代記『幸福書房の四十年 ピカピカの本屋でなくっちゃ!』が出版された。
僕も何気なく使っていた町の屋が、なぜ閉店に至る決断をしたのか? それを悲壮感漂うことなく、正直に、かつ切実に語るじつに潔い本である。そして、町の小さな書店経営者が今どんな現実と向き合っているかを知る最良のケース・スタディだとも思う。
短い章立てを重ね、本屋を続ける難しさと喜びを語る岩楯さん。電子部品製造メーカーに勤め、好きな五木寛之や野坂昭如を中心に文芸誌を読み漁っていた青年が一念発起、自身の書店をつくろうと決意したのは28歳のとき。時代は1977年だった。
本書は文体が簡潔で淡々とすすむ。「店売」と呼ばれる問屋での仕入れの楽しさやお客さんとの無言のコミュニケーションなど、岩楯さんが本屋の現場で何を意気に感じていたのかがよく伝わってくる。例えば、岩楯さんは「幸福書房」の常連鉄道ファン26〜27人の顔をすぐ思い浮かべることができ、彼らのために仕入れをする。でも、「○○さん、この本仕入れておきましたよ!」などと声は掛けない。彼は棚にそのオススメ鉄道本を2冊だけ差し(通常は1冊)、本棚を通じて寡黙にお客様と対話をするのだ。
しかしながら、20年前の最盛期に1日45万円程(月商1400万円)あった売り上げは少しずつ減少し、2017年には1日15万円になってしまった。家賃35万円の代々木上原店で平均77〜78%くらいの仕入れ下代だと、どうしても経営は難しくなる。さらにいうなら、取次が定める月末の締め日と月末3日前に締め切られる返品との時間差が資金繰りに大きな影響を及ぼすという。
この本のよい点として、売り上げなどの数字や出版業界の慣習を赤裸々に開示し、日の元にさらした点は見逃せない。現代でなぜ小さな書店が成立しにくいのか? を感情や心意気ではなく、制度も含めて冷静に検証することは必要だ。
自分のことに翻って考えるならば、僕は本を売り続けることの難しさを痛感し、本を選ぶアイデアや本のために整える環境を売っているといえる。それを逃げだという人もいれば、賢明だという人もいるが、じつのところ他者の評価は気にならない。「好きなものにしがみつきながらどうやって生きていくのか?」という自分なりの執念で導き出したやり方だ。そういう一人の本好きとして、本書の読後は熱くならざるを得なかった。勇気ある撤退を行った彼の明るい遺言のような本書を読んで、「幸福書房」の屍を自身はどうやって越えていくべきなのか? を今日も考える。そして、今後もっと厳しくなる本の世界で、楽しく考え続けることを、ここに誓います。
もちろん、豊島区の南長崎に「ブックカフェ 幸福書房」が黄泉帰ることも待っていますよ!